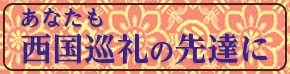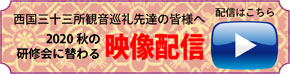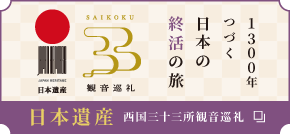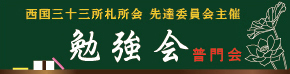第一番 那智山 青岸渡寺

那智山は熊野三山の一つ。熊野信仰の霊場として長い歴史がある。もともと那智の滝を中心にした神仏習合の一大修験道場だったが、明治初期に青岸渡寺と那智大社に分離した。今も寺と神社は隣接していて、双方を参拝する人が多い。
参詣ガイド 地図 大きな地図で見る
- 住所
- 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8番地
- 交通
-
- JR京都,新大阪,天王寺より、JR名古屋より勝浦下車 路線バス タクシーあります。
- バス、自家用車は阪和自動車道からR42号線
- また、名古屋方面からは伊勢道勢和多気ジャンクション、熊野街道大台でR42号線に乗り那智山道へ
- 駐車場
- 有 (附近バス50台,自家用車300台)
- 拝観料
- 不要
- 拝観時間
- 7:00〜16:30
- 納経時間
- 7:30〜16:30
- 電話
- 0735-55-0001
- FAX
- 0735-55-0757
- ウェブサイト
- https://seigantoji.or.jp/
| 一月一日~七日 | 修正会 |
|---|---|
| 二月節分 | 豆まき大法会(本尊開扉) |
| 三月彼岸一週間 | 大法会 |
| 四月 | 開山祭献茶法要(本尊開扉) |
| 八月十七日 | お盆精霊追善大法要(本尊開扉) |
| 九月彼岸一週間 | 大法会 |
| 十一月 | 大黒天七福神大法会 |
「補陀洛(ふだらく)や岸打つ波は三熊野(みくまの)の那智のお山にひびく滝つ瀬」と御詠歌で親しまれている西国第一番の札所であります。当山の縁起に開基は仁徳帝の頃(4世紀)。印度天竺の僧、裸形(らぎょう)上人が那智大滝において修行を積みその暁に滝壷で24cmの観音菩薩を感得し、ここに草庵を営んで安置したのが最初です。
その後、200年推古天皇の頃、大和の生佛上人が来山し、前述の話を聞き一丈(3m)の如意輪観世音を彫み、裸形上人が感得した24cmの観音菩薩を胸佛に納め勅願所として正式に本堂が建立されたのです。
平安朝中期から鎌倉時代には、「蟻の熊野詣」といわれ、熊野三山の信仰がさかんになり、この時、65代花山法皇が三年間山中に参籠され那智山を一番にして近畿各地の三十三観音様を巡拝されましたので、西国第一番札所となりました。
現在の本堂は織田信長南征の兵火にかかり、天正18年(1590)豊臣秀吉によって再建され、桃山時代の建築をとどめ南紀唯一の古い国指定の重要文化財建造物で、この堂の高さは18mで、大滝の落口の高さとおなじであるといわれています。
青岸渡寺尊勝院は、中世以降は天皇、皇族の熊野詣での宿泊所にあてられていました。不開門は同院の入り口にある唐破風の四脚門で有名。なお、大正7年に那智の滝参道口・沽池と呼ばれるところから発掘された、飛鳥・白鳳時代から鎌倉時代初期にかけての熊野信仰を知る貴重な那智経塚出土品のうち、白鳳、奈良時代の観音菩薩立像、また藤原時代後期の金剛界三昧耶形(曼荼羅を立体的に表現)が国指定重文になっています。境内からは那智の滝、那智原始林、太平洋の眺めもよく、南北朝時代の重文・宝篋印塔(4.3m)や梵鐘があります。
札所一覧
- 第一番 青岸渡寺
- 第二番 金剛宝寺
- 第三番 粉河寺
- 第四番 施福寺
- 第五番 葛井寺
- 第六番 壷阪寺
- 第七番 岡寺
- 第八番 長谷寺
- 第九番 南円堂
- 第十番 三室戸寺
- 第十一番 上醍醐 准胝堂
- 第十二番 正法寺
- 第十三番 石山寺
- 第十四番 三井寺
- 第十五番 今熊野観音寺
- 第十六番 清水寺
- 第十七番 六波羅蜜寺
- 第十八番 六角堂 頂法寺
- 第十九番 革堂 行願寺
- 第二十番 善峯寺
- 第二十一番 穴太寺
- 第二十二番 総持寺
- 第二十三番 勝尾寺
- 第二十四番 中山寺
- 第二十五番 播州清水寺
- 第二十六番 一乗寺
- 第二十七番 圓教寺
- 第二十八番 成相寺
- 第二十九番 松尾寺
- 第三十番 宝厳寺
- 第三十一番 長命寺
- 第三十二番 観音正寺
- 第三十三番 華厳寺